【書籍と著者の紹介】
二つの祖国のために「丘を越えて、海を越えて」
~わが生涯の友『山崎洋の仕事集』
高木 一成
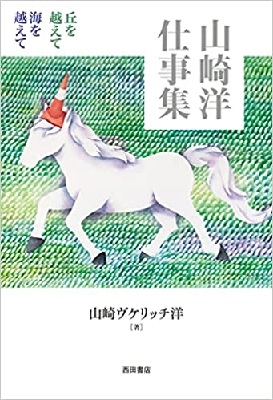
五月末に西田書店の日高氏から、「山崎ヴケリッチ洋『山崎洋仕事集 海を越えて丘を越えて』がついに刊行となり、寄贈本の発送作業を始めました」との連絡をいただいた。数日後には宅配便が届く。私は山崎君の知友として、構想の段階から同書に関わり、とうとう長文の「後記 山崎洋君のこと」を書かされるはめになった者として、特別の感慨をもってページを繰っていた。すると、山崎君から連絡があり、メールマガジン「オルタ広場」に感想文を書いてほしいと言ってきた。「初岡さんのアイデアなんだ」という。初岡昌一郎氏は、山崎君のベオグラード留学当初からの知り合いで、初岡氏に言われると断れないのだそうだ。山崎君の著作とはいえ、私にとっては自分で書いた「後記」以外の部分についても、何度も相談にのった本である。感想というには思い入れが強すぎる。しかし、山崎君の分身を自負する者として、「イッセイちゃん、頼むよ」と言われると、私も嫌とは言えない。結局、こうしてコンピューターに向かうことになった。「後記」を書き終えたときには、物書きの真似はもう二度としたくないと思っていたのだが。
表題の『山崎洋仕事集』というのは、見慣れない言葉だが、山崎君の説明では、編集者の日高氏の提案によるものだそうだ。論文集、作品集、随筆集など、「集」のつく表題は少なくない。だが、本書に採録された五一篇の作品は、論文、記事、随筆など、さまざまなジャンルに及ぶ。そのどれにも当てはまるのが「仕事」という言葉である。便利な言葉だ。初案は「全仕事」だったが、発表されたものをすべて並べることは無理だし、また山崎君の活動の大きな分野である翻訳作品は対象外でもあるし、結局、「全」の文字は消えたという。
山崎洋君
「山崎洋」はもちろん、著者の名前で、ヤマサキ・ヒロシと読む。ここ数年、「オルタ広場」に投稿していたから、名前を見たことのある読者もおられるだろう。帯の下に印刷された著者名は「山崎ヴケリッチ洋」となっていて、こちらが現在の本名である。いわゆるゾルゲ事件に連座して網走で獄死したユーゴスラビアのジャーナリスト、ブランコ・ヴケリッチと日本女性、山崎淑子のあいだに生まれた一粒種で、父の死によって母方の戸籍に登録された。本書に採録された諸論稿の執筆時には「山崎洋」とのみ署名している。「後記」にも記しておいたが、姓に「ヴケリッチ」を加えるのはあとのことだ。ただし、ユーゴ内戦時に書かれたいくつかの報道記事は、「武家利一」の筆名で発表された。「ヴケリッチ」の漢字表記で、父の遺産である。
余談になるが、山崎君の話では、山崎家の祖先は越後の出身で、武家を廃業し、江戸に出て日本橋で米問屋を営んでいたそうで、本来はヤマザキと発音した。淑子さんの世代に、ローマ字表記でサインするとザの「ℨ」が下に出るのを嫌い、「s」を使うようになった。一族の中には今もヤマザキを名乗る者がいる。また、漢字の「崎」を「﨑」と書く者もいる。山崎君自身は戦後すぐ、小学校に入学したとき、祖父の金作氏が手作りのノートに墨で「山崎ヒロシ」と名を書いてくれたので、「崎」が正しいと信じていると言っていた。姓名判断で「一画多ければ大幸運でしたね」と言われたが、山崎君は、「僕は十分、運がいいよ」と言って、「崎」を「﨑」に改めて一画増やしたりはしなかったとか。
※『山崎洋の仕事集』について
本書は、「はじめに」で著者自身が説明しているように、山崎君がこれまでの半世紀に日本の論集や雑誌、新聞などに発表してきた論稿のほか、印刷されることのなかった講演原稿までを集めて一冊にまとめたものである。
三部から成る。それは上に述べたジャンルの違い(研究論文、報道記事、その他)を反映しているが、同時に書かれた時代の差異をも表している。
すなわち、第一部は、一九七〇年代から八〇年代にかけて、独自の社会主義として国際的にも注目を浴びたユーゴスラビアの「自主管理社会主義」の制度や理念をテーマにした論文から成る。この時代は、研究対象の消滅によって終わりを告げた。社会主義を知らない若い世代の読者には、難しい議論のように響くかもしれないが、一読の価値はあるだろう。山崎君の言葉を借りれば、「葬られた理念の中にしばしば真理がある」からだ。私の世代には当時、現代資本主義の矛盾を考え、西欧諸国の左翼思潮に関心を持った者もいた。そういう読者には、懐かしい部分にちがいない。
第二部は、九〇年代の不幸なユーゴ内戦の記録だが、報道といっても、事件現場に駆けつけて関係者の話を聞くという、私たちの知っている新聞記者の手法とは少し違うようだ。山崎君は事件の推移を見つめ、入手可能な報道や資料を分析し、頭で再構成していく。歴史家の手法に近い。山崎君は、現場に行くと、印象の強さで合理的な判断が狂うこともある、と説明していた。引きこもり症の著者の言い訳とも取れる。だが、とくに戦争については、戦線にどちらの側から近づくかで、「白」「黒」の判定が分かれるのが普通であろう。銃弾を撃ち込んでくる側が敵であり、「黒」だからだ。どちらの側で取材するかを選ぶ段階で、すでに答えが出ていることも多い。もちろん、報道であるかぎり、時間的な距離を置いて事件を客観的に見る余裕はない。関係資料の多くも秘匿されたり、破棄されたり、当事者の必要に応じて書き替えられたりしているので、事件に至るまでの経過を資料によって完全に再現することはできないだろう。
事件を時系列的に見る必要から、第二部には、内戦に先立つ期間に書かれた小記事もいくつか採録されている。チトー時代のユーゴにおける婦人や青年の解放的な実態や、チトー後の混乱期における庶民のしたたかな生き様を知ることは、民衆は戦争の機動力ではなく、犠牲者であることを理解するために有効だと思う。ユーゴスラビアを構成する共和国の政治指導部や、それを操る「国際社会」にこそ戦争勃発の責任があるのだ。この時代は、ユーゴスラビアが解体され、内戦が終息し、報道対象が消滅することで終わる。正確にはメディアの関心が他に移っただけである。多くの問題が未解決のままに残り、「国際社会」の不断の介入を可能にしていると、山崎君は考えている。本書の上梓に先立ち、山崎君の「コソボ問題」に関するコメントが「オルタ広場」に掲載された(⋆編集部注:オルタ広場23年4月20日号「NATO空爆とコソボの悲劇」)が、まさにコソボが好例である。コソボ共和国ではNATOの支援を受けた多数派民族当局の権力による非アルバニア系住民への抑圧が強まっているだけでなく、将来に希望を持てないアルバニア系住民の外国への移住も続いている。山崎君の話では、最近の二年間に二〇万の人口が流失したという試算があるそうだ(ポリティカ紙、2023年5月29日)。
第三部は、世紀が変わり、新千年紀が始まるころから現在までの期間の随筆等や講演原稿、音楽会での挨拶や美術展のカタログに寄せた小文など、多様な形式の文から構成され、先行の二段階を経て山崎君が到達した思想信条が吐露されている。帯にも引用された「戦争は真実が死んだときにやってくる」とか、「異文化間の交流もまた、単に違うものを互いに認め合い、相互理解を深めるための架け橋を築くというのでは十分ではない。異なって見えるものが実は同じ人間の営みであり、ひとつの本質の異なった表れにすぎないことを知らなくてはならない」とかいった言葉は、不条理に満ちた現代社会に直面した山崎君の苦悩や困難から導き出された結論なのだろう。
この時期はまた、著者の翻訳者としての活動が頂点を迎えた時期でもある。父の国と母の国の交流という山崎君の使命がもっともよく満たされた分野が翻訳活動だった。セルビア語から日本語へ、『ブランコ・ヴケリッチ 日本からの手紙』(未知谷)をはじめ、セルビア文学の古典といえるニェゴシュの叙事詩『山の花環/小宇宙の光』(幻戯書房)、ノーベル賞作家イボ・アンドリッチ『イェレナ、いない女他十三篇』(同)、現代作家ドラゴスラヴ・ミハイロヴィッチ『南瓜の花が咲いたとき』(未知谷)などを翻訳した。また日本語からセルビア語への翻訳には、『ブランコ・ヴケリッチ 獄中からの手紙』のほか、『古事記』、『万葉集(抄)』、『竹取物語』、『おくのほそ道』、『芭蕉名句選』、『蕪村名句選』、『江戸名句選』などがある。こうした作品の翻訳が山崎君の思索になんらかの影響を及ぼしたであろうことは、推察に難くない。翻訳はもっとも有効な読書の方法だと、山崎君は常々、口にしていた。
本書を見ると、著者の生涯のまとめとして構想されていることが分かる。本来は本書の「解説」であるべき「後記」が、「伝記」的要素の強い内容に傾斜してしまったのは、単に私の力不足によるだけではない。この本そのものが波乱に満ちたひとつの人生の表現なのである。
「伝記」といっても、完全なものではない。所詮、他者である私が見、聞き、知ることのできた範囲を出ることはない。山崎君の人生は八二年に及ぶ。テキストが自然と長くなる。編集者のご好意で、当初予定のページ数を大幅に超えてしまった。それでも私が面白いと思って原稿に書いたエピソードで、山崎君の希望で消去した部分も少なくない。
たとえば、「後記」には、山崎君が玉川学園時代にデンマーク体操を学んだ話がある。実は父のブランコ・ヴケリッチの先妻エディットが指導員の資格を持ち、来日してしばらく玉川学園で教えていたという。不思議な縁を感じて書いた。その後日談。山崎君は、かつての同級生に頼んで、その事実を調べてもらったのだそうだ。その結果、玉川学園出版部刊行の小原國芳編纂「労作教育研究46」(昭和8年5月)に、次の一文が見つかった。「クローンさんが歸ることが決つて、私共は又この度その代りにエテツツ・ウイツクリツツさんをお迎へした。ウツクリツツさんの夫君は、ユーゴースラビア人であつてパリーの大新聞の記者、國際聯盟を日本が脱退して國際問題が混み入つて來たとき、各國から有數な記者が乘込んで來たがウイツクリツツ氏もその一人。東京で各方面に活躍されてゐる。ウイツクリツツ女史はその夫人、丁抹人で昨年度のオーロロツプ卒業生でとても熱心に教へて下さる。この夏は私共と一緒に新潟はじめ諸々に出懸けることになつている」(原文ママ、58頁)というのである。なんとか残したかったが、後日談が多すぎるので、泣く泣く切った。
もうひとつの例は、一九七七年、川崎市とクロアチアのリエカ市とのあいだに調印された姉妹都市協定の話。ある日、山崎君は社会党の飛鳥田一雄氏から連絡を受けた。「今、ベオグラードに来ている。ホテルに来てほしい。自主管理の話を聞きたい」と言う。飛んでゆくと、伊藤三郎川崎市長が一緒だった。山崎君の話を聞いていた伊藤市長は「難しいですね」と顔をしかめ、「質問があります」と言う。「どうぞ、なんでしょう」。「ご存じのように川崎市は京浜工業地帯の中心都市ですが、公害問題に悩まされています」。山崎君は船で東京湾に入ってきたときに見た黒いガスの蓋を思い出した。「知っています。川崎といえば喘息ですからね」。「市民が革新市政を選んだのも、その問題の解決を期待してのことでしょう」と、伊藤市長は言い、「だが、もうひとつの問題がある。百万都市なのに東京と横浜のあいだに挟まれて存在感が薄い。国際都市として発展させたいと思い、姉妹都市提携を考えています」と、付け加えた。「市議会では、与党の革新政党は中国を推し、野党自民党はアメリカの都市を求め、まとまらない。いずれ両方やるけれど、最初が肝心です。お話では、ユーゴは第三の道を行くらしい。適当な姉妹都市候補はありませんか」。山崎君は一瞬、答えに窮したが、ピンとくるものがあった。「クロアチアのリエカはどうでしょう。リエカとは川の意味だから、同姓同名。港湾都市で、大きな造船場があるから工業都市ともいえる。日本へは貨物船の定期航路があるので、船員で日本に行った人も多い。隣のオパティアの町には船員が持ち帰ったという椿が大きく育っていて、町の花に指定されています」。「うちも椿が市の花ですよ」。「それはいい。でも、問題がふたつあります。ひとつは、リエカの海は近くに観光地や海水浴場があり、港内でも汚染が少ない」。「それは問題ではない。我々は公害対策模範都市を目指すので、こういう風にきれいな海にしたいと言えば、理解が得られますよ」。「もうひとつは、ユーゴとしてはそこそこの都市ですが、川崎に比べれば人口があまりにも少ない。もっとも、観光シーズンには、外国からの観光客で三〇万に膨れ上がりますけどね」。「それでいきましょう」。こうしてリエカが選ばれたのだそうだ。山崎君が留学に行ったとき、最初の一歩を印した町だと思えば、何かの因縁だろう。川崎市の使節団の通訳として、何度かリエカを訪れることになった。このエピソードは、山崎君が「セルビア民族主義者」でないことを示すもので、初案に入っていた。ただ、後味の悪い後日談があり、結局、削った。クロアチアの内戦が始まったとき、川崎市は使節を派遣し、リエカ市に援助物資を届けたが、リエカ側の担当者は何でこんなものをと言わんばかりに、「私たちに必要なのは武器です」と言って、川崎市の代表を落胆させたというのだ。その話を、山崎君は聞いていたのである。
そのほか、名前を聞けばえっと思う有名人との出会いも、枚挙に遑がないが、すべては書けなかった。山崎君の話では、日本でも、ユーゴスラビアに渡ってからも、愛情をもって接してくれた人、親切にしてくれた人、支援を惜しまなかった人は数知れないという。とくに留学当初の不安がいっぱいのとき、父ブランコ・ヴケリッチのかつての同志たちや東京のユーゴ大使館に勤務していた人たちに助けてもらった。ベオグラードの日本大使館の館員や朝日新聞、NHKの支局長、日本商社の支店長にも世話になった。留学生仲間もいた。私の直接、知らない人がほとんどで、一部を除いて、いちいち名前を挙げることはしなかった。この本は、そうした、山崎君の人生を支えたすべての人に捧げられている。
「人生は旅である」とは、松尾芭蕉の翻訳者である山崎君が好んで口にする文句だが、実際、山崎君の生涯は「旅」であったと言えよう。遥かな昔、一九六三年に、大学を卒業したばかりの山崎君が二カ月の船旅を経て、父の国ユーゴスラビアへ留学した事実は、本書の副題「丘を越えて海を越えて」に表現されている。その後も、ユーゴ国内はもちろん、欧州全域を東から西までくまなく旅したという。アメリカ合衆国もロスアンジェルスからニューヨークまで横断した。私がニューヨークの駐在員になる前である。どちらかと言えば出不精で、引きこもりがちの現在の山崎君からは想像できない。コロナ禍で外出禁止になり、息子さんにこぼしたら、「普段と変わらないじゃない」と、まったく同情されなかったという人だ。
ユーゴ解体後、旅行は減ったが、それでもベオグラードのアパートの自室に籠ったまま、四カ国を回ったと言う。それはもちろん、山崎君らしい冗談で、彼の住む地域がユーゴスラビア社会主義連邦共和国からユーゴスラビア連邦共和国(新ユーゴ)、セルビア・モンテネグロ、セルビア共和国へと、目まぐるしく国名と領土を変えたことを言っているのである。
だが、物理的な移動だけが「旅」なのではない。社会主義経済の研究から、内戦の報道、文学作品の翻訳まで、活動分野の移動もあった。肩書も研究者、ジャーナリスト、翻訳家と変わる。それに伴い、視点や手法や文体も変わる。目標を追い、挫折し、また新たな理想を求め、迷路に迷い込む。表紙の、緑の野原を駆ける一角獣の図は、画家である三男の光君の作品だというが、題名を見ると、仕事がなく原を彷徨う無政府主義者の姿らしい。自画像だろうが、お父さんにも当てはまりそうだ。私のように商社勤務で、勤務地は転々としたが、仕事は実務一筋でやってきた者から見ると、この移動は精神的負担を伴い、苦労が多かったのではないか。
山崎君は、それを水の流れに譬えている。私が「後記」の末尾に記録した山崎君の言葉を最後に引用しておこう。
「人生は川の流れと同じ。水は高きより低きに流る。上に行こうと焦れば大変だが、流れに身をまかせてくだるのは自然だ。岩に当たって砕けたり、淵に落ちて沈んだりしないように気をつけるだけさ。最後は、大洋に流れ込む。それが洋の定めさ」。
『山崎洋仕事集 丘を越えて海を越えて』が一人でも多くの読者の目に触れ、心を捉えることを願い、本稿を閉じることにする。
(2023.6.20)
編集事務局注:『山崎洋仕事集 丘を越えて海を越えて』の書籍はこちらから
購入できます。https://amzn.to/3CAev6w
山﨑洋氏のオルタ広場への過去のご寄稿はこちらから。
オルタ広場60号(2023.4.20)NATO空爆とコソボの悲劇
オルタ広場52号(2022.8.20)【往復対談】「現代において『正義の戦争』-『戦争の正義』がありうるか」を読んで
オルタ広場49号(2022.5.20)セルビアから見たウクライナ戦争
オルタ広場26号(2020.6.20)コロナの春、ベオグラード便り
その他本文で紹介されている書籍も下記からリンクしています
・『ブランコ・ヴケリッチ 日本からの手紙』
・セルビア文学の古典といえるニェゴシュの叙事詩『山の花環/小宇宙の光』(幻戯書房)、https://amzn.to/3CxSvZY
・ノーベル賞作家イボ・アンドリッチ『イェレナ、いない女他十三篇』(同)、https://www.genki-shobou.co.jp/books/978-4-86488-209-5
・現代作家ドラゴスラヴ・ミハイロヴィッチ『南瓜の花が咲いたとき』(未知谷)https://amzn.to/46anadc
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧