【【コラム】ザ・障害者】
用語の再定義/(著書紹介)『障害者から「共民社会」のイマジン』
社会モデル― 社会モデルに先立つ医学モデルは、医療的治療の限界を受けてもはや治癒できない固定した状態を「障害」と定義した。リハビリテーション、訓練によって障害の軽減、または残存機能を最大まで高めることが求められた。
これに対して、社会モデルは、障害という属性をもつ人と社会環境との間に「障害」が存するとし、したがってバリアフリーがその中心課題となる社会システムの変更、合理的配慮の提供が求められる。
さらに、これに対する私のもう一つのオルタナティブな、本来あるべき「社会モデル」を再定義すれば、障害という属性には限定しない。障害者のみならず社会的に排除された人すべて、ひきこもり・ニート、依存症者、刑余者、片親世帯、ホームレスの人、困窮者など、また被差別部落、アイヌ、沖縄、在日など歴史的に差別される人、その排除の一切の原因が社会にあるとみる社会モデル、すなわち、社会が排除の対象者を新たにかつ歴史的に作り出すことを意味する。
少子化対策― 少子高齢社会があたかも自然現象であるかのように流布され、単なる社会現象とみられている。そのため、たとえば待機児童対策が、しかしそれは対処療法的二次対策であって、根本的解決には至らない。
七〇年代半ばは「家付き、カー付き、ババ抜き」、バブル期は「三高(高所得、高学歴、背が高い)」、リーマンショック時には「公務員」。これは結婚適齢期にある女性の結婚相手の願望。日本ではフランスと違って結婚を前提に子どもを産む国民性、そのため、適齢期の女性は非正規労働者を選ばない、相手にしない傾向にある。
正規より非正規の男性の未婚率は二倍。政府は少子化対策と言いながら、一方では今や非正規労働者を四割にまで、そんな不安定雇用を増やす経済政策をとっている。少子化対策はすなわち安定雇用政策。
合成の誤謬― これは近代経済学の概念であって、一つひとつの行動は正しいのだが、それが集合化・総合化されると、結果は誤りとなる誤謬となって現れる。
それを再定義すると、森友・加計、財務省、防衛相、厚労省の一つひとつは誤りであっても、安倍政権・総理官邸に集約されると、合成の整合性になる。
多様性― 私の「多様性・多様な」は、一人ひとりが千円をもって、日本蕎麦屋、中華屋、イタリアン、ピザカフェ、千ベロ居酒屋に行く事である。
安倍総理の「多様性・多様な」は、一万円をもった紳士は高級レストランに、一人五千円会費の女子会に、千円をもったサラリーマンは日本蕎麦屋に、五百円をもった契約社員は駅構内の立ち蕎麦屋に。
そしてもう一つの重要な再定義は「専門性」。特別支援学校の分離に基づく、分離のための専門的教育・・・・・。
(元参議院議員・共同連代表)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆書籍紹介◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『障害者から「共民社会」のイマジン』
堀 利和/著 社会評論社
四六判並製224頁 定価=本体1,700 円+税 ISBN978-4-7845-2411-2
我ら障害者は社会的弱者・サバルタンである。
しかしそれだからこそ、我ら障害者は社会を変える社会変革の主体者でもある。
<主要目次>
序章 「共生社会」へのイマジン
第1部 障害者か健常者かそれが問題だ!
第1章 共生/第2章 共働/第3章 共学/第4章 共飲
第2部 コラム ザ・障害者
第5章 影から光が見えてくる/第6章 世界の類のない日本の盲人史
/第7章 日常の日常の羅針盤/第8章 世の中の現象学/第9章
主体探しの旅/第10章 もう一つのアジア障害者国際交流モンゴル大会
終章 理論と実践からのオルタナティブな視座
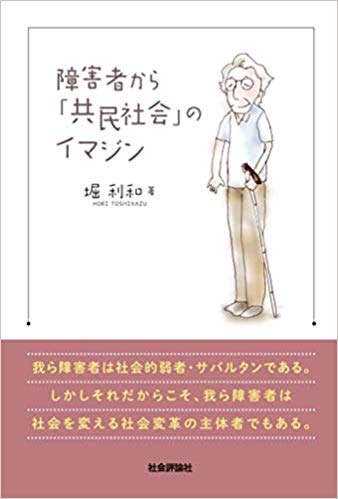
<編集者より>
「市民社会」を変革する「共民社会」の構想のために
著者の堀利和は静岡市の小学校入学直後、スティーブンジョンソン病という難病になり、その後遺症で弱視になったため、静岡盲学校に転校する。その後、東京教育大学付属盲学校に転入し、そこから明治学院大学に進学する。卒業後、保育園の産休補助の保父、養護学校のスクールバスの添乗員、点字講習会の講師として働く。そして参議院議員を12年間務める。
現在、障害のある人ない人が共に対等に働く事業所づくりをしているNPO法人共同連の代表。さまざまな障害者運動や地域の活動にかかわりながら、労働力の商品化・市場経済を前提とする現在の「市民社会」を、共同社会に向けて変革するための問題提起を精力的に展開している。
本書に収録したさまざまな論考は、この間の著者の発言集です。「市民社会」から「共民社会」へという構想の多様な素材をそこから読み取ることができるでしょう。
<著者紹介>
ほりとしかず NPO法人共同連代表。『季刊福祉労働』編集長。
著書に『日本初 共生・共働の社会的企業―経済の民主主義と公平な分配を求めて』(現代書館)『アソシエーションの政治・経済学 ―人間学としての障害者問題と社会システム』(社会評論社)『私たちの津久井やまゆり事件―障害者とともに︿共生社会﹀の明日へ』(編著、社会評論社)など多数ある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧