【海峡両岸論】
「新冷戦論」の落とし穴にはまるな
~コロナ後の世界の2潮流を読む
新型コロナ・パンデミックが続く中、二つの潮流が国際政治を覆っている。第1は米国のグローバル・リーダーからの退場。第2に弱体化した国家の復権である。いずれも以前からあった流れだが、コロナ禍がそれを加速させている。グローバル協力に代わって国家が鎌首をもたげ、米中の戦略的対立があらゆる領域で繰り広げられる。メディアはそれを「米中覇権争い」[注1]や「米中新冷戦」=写真=などと、おどろおどろしいタイトルで伝える。だが米中対立を「新冷戦」と規定することこそ、我々を身動きできない思考の「落とし穴」に誘う。

Newsweek Japan(6月16日)表紙
◆ グローバル化と多国間協力
米国のグローバル・リーダーからの退場については恐らく異論はないと思う。そこで「国家の復権」を少し説明したい。
1989年の冷戦終結は、政治的にも経済的にも「資本主義陣営」と「共産主義陣営」に分かれていた世界を、少なくとも経済的には「一つ」に変えた。ヒト、モノ、カネが国境を越え移動する地球規模の経済システムのスタートである。世界中に複雑に張り巡らされたサプライチェーン(部品調達・供給網)を支配する多国籍企業は、国家主権に属する金融・通貨政策をはじめ、雇用・賃金など一国の経済・社会を支配する実権を国家から奪っていった。新自由主義がリードする「グローバリズム」と呼んでもいい。ここでは、ヒト、モノ、カネの自由な移動を意味する「グローバル化」とは区別して使いたい。
グローバル化は多国間協力と統合を促し自由貿易と経済連携が進み、欧州連盟(EU)や東南アジア諸国連合(ASEAN)は求心力を高めた。しかし世界保健機関(WHO)によるパンデミック宣言(3月11日)は、各国に国境を閉鎖させ、グローバルなサプライチェーンを破断し、世界中で生産停止ないし停滞が始まった。
1929年の「大恐慌」で世界は10年に及ぶ深刻な不況を体験した。「震源地」だった米国をはじめ各国が採用したのが、ケインズの「有効需要論」に基づく「社会主義的」政策である。市場「至上主義」に代わり、国家が景気回復のため減税し、失業者を雇用する国家主導型の経済政策だった。
◆ 国権回帰が加速
話をコロナに戻す。世界の感染者のほぼ四分の一、死者数が12万7,000人(7月2日現在)を超えた米国では4月の失業率が14.7%と過去最悪を記録(米雇用統計)。ダウ工業株も3月12日、過去最大の下げ幅を記録し、大恐慌を超える深刻な不況が進行している。
コロナ感染を過小評価して、初期段階で無策のまま放置したトランプ政権だが、経済指標の急下降で一人1,000ドル(13万円)を4月に現金支給するなど、計2兆2千億ドル(約238兆円)の経済対策を成立させた。安倍政権も5月末、補正予算としては過去最大の約32兆円の第2次補正予算案を閣議決定し、安倍は「空前絶後の規模で世界最大」と自画自賛した。
こうした国家主導型政策が意味するのは、グローバル化で退場した「国家の復権」に他ならない。多国籍企業には世界経済をリードする力はあるが、疫病と失業、貧困に苦しむ市民に、救いの手を差し伸べる意思や能力は希薄である。企業倒産と失業者に経済支援できるのは国家だけ。いま目の前で繰り広げられているのは、こうした主役交代の風景である。
コロナ禍は「グローバリズム」がもたらした格差拡大に疲れきった世界に、国権回帰を加速させた。
国権回帰はどんな変化をもたらすのか。ざっと言えば次の二点。多くの国は国際協力より国益を優先し、国民もまた強権国家を望む傾向である。先進国を覆っているポピュリズムの加速と言ってもいい。
具体例をみる。中国政府が「武漢封鎖」という荒療治に出た時、「独裁国家だから」という見立てが溢れた。では米国、英国、イタリアなど多くの西側先進国が、私権を制限し罰則を科すロックダウン(都市封鎖)=写真=に出たことをどう説明すればいいのか。それが感染拡大防止という、緊急かつ一時的な政策だとしても。

封鎖下のローマ・コロッセオとマスク姿の通行人
日本でも同様の現象が起きた。3月末から感染者が急増すると、反安倍勢力も「緊急事態法」に踏み切れない安倍に苛立ち、発動を促した。強権への期待が日本でも芽生えている兆候ではないか。
◆ 問われる民主の存在意義
「世界最大の民主国家」インドのモディ政権は3月25日から全土封鎖の強権を発動し、ハンガリーのオルバン政権は政府権限を強化する「非常事態法」を成立させた。ロシアや中欧・東欧諸国では、既にあるポピュリズムの土台の上に、コロナ対策を理由にした強権政治が勢いを増している。
「国益優先」の例も挙げる。中国が「一国二制度」を採る香港に7月1日、香港政府を飛び越え「国家安全維持法」を導入したのは、中国側の論理からすると、欧米による「カラー革命」という内政干渉に対抗し、「主権」にレッドラインを引いたことを意味する。
コロナウイルスの発生源に関する独立調査を求めたオーストラリア政府は、中国から農産物輸入を規制する「報復」を受けた。同国の輸出の3割は中国向けで、経済への影響は少なくない。だが対中強硬姿勢を貫くモリソン首相の支持率は66%と、なんと年初の2倍に上昇した。
強権国家を望む声は、「小さい政府」(新自由主義)を採用してきた先進民主国家で顕著である。それは、危機に直面した時の「民主システム」の非効率性と制度疲労の顕在化が一因だ。民主システム自体が、その内容と存在意義を問われている。民主を「錦の御旗」掲げる声は後を絶たないが、民主とは統治のプロセスであって、目的化してはならない。
◆ 「米ソ冷戦」とは何だったのか
「国権回帰」はこの程度にし、「新冷戦論」に移ろう。トランプ政権は2017年12月に出した「国家安全保障戦略報告書」で、中国を「戦略的競争相手」とし、貿易不均衡のみならずデジタル技術や軍事、文化などあらゆる領域で、中国を敵と見なす戦略を打ち出した。「新冷戦論」の綱領的文書である。
米中関係を「新冷戦」と規定するのは正しいのか。それを検証するには、冷戦期の「米ソ冷戦」の特徴と構造を明らかにしなければならない。
特徴の第1は、世界が資本主義陣営と社会主義陣営の2ブロックに分かれ、経済のみならず体制の優位を競い合うイデオロギー対立だった。
第2に、米ソ対立の構図が日本を含め各国の内政に投影され、政治対立・抗争が繰り広げられた。
第3は、米ソは核軍備・軍縮体制を整備し、直接軍事衝突を避け衛星国に「代理戦争」を押し付けた。
◆ 「チャイナ・スタンダード」はない
それを念頭に米中関係をみれば、
① 体制の優位を争ってはいない
② 対立が各国の内政にそのまま投影されてもいない
③ 代理戦争もしていない。
「体制の優位」については少し説明が必要だろう。論点の第1は、北京は米国が築いてきた「アメリカン・スタンダード」に代わって「チャイナ・スタンダード」を主張しているのかどうか。中国は確かに、今世紀半ば(建国100周年の2049年)に「世界トップレベルの総合力と国際提携協力を持つ強国」(習近平 第19回共産党大会演説)の「夢」を描いている。だが中国のガバナンスを、普遍性を持つ「チャイナ・スタンダード」として主張しているわけではない。
「人類運命共同体」という世界観も掲げる。しかし、そこで想定される秩序は「多極化」と「内政不干渉」にある。中国は「社会主義強国」実現のため、資本主義世界を不可欠な存在とみなすパラドクス(逆説)を生きている。
◆ デカップリングは相殺される
第2の論点は、コロナ後の世界がブロック化されるかどうかである。経済再建のカギは、国境封鎖で目詰まり状態の「サプライチェーン」(部品の調達・供給網)の再構築だ。グローバルな相互依存関係が復活するかどうかである。
トランプ政権が仕掛ける「新冷戦」は、世界経済を中国と二分する「デカップリング」を厭わない。華為技術(ファーウェイ)=写真=と中興通訊(ZTE)の大手2社の排除がその典型。ついでに言えば、安倍政権が2019年7月、半導体原材料の対韓輸出規制に出たのも「ミニ・デカップリング」だった。

Huawei Japan HPより
デカップリングによって世界経済が「ブロック化」すれば、米ソ冷戦時代の第1の特徴と似た世界が再現されるかもしれない。デカップリングへの対応をみる。ファーウェイは米国の排除に対し、スマホ領域ではGoogleなど米国製ソフトに頼らず、自前の「オフィス」の開発を急いでいる。中国はさらに自国の半導体産業育成に資金を投入し、韓国も独自の化学産業を立ち上げている。
トランプ政権が「軍事技術」とみなすソフトや部品のサプライチェーン再構築を阻止するのは可能だ。しかし、排除される側は自前の技術開発を加速しキャッチアップする。デカップリング効果は相殺される。
◆ 「地球規模の金融システム」がカギ
ブロック化に否定的な主張を挙げよう。現代国家は
①地球規模の金融システム
②サプライチェーン
③ 情報ネットワーク
の「三本の鎖」に組み込まれ、完全に依存している[注2]と見るのは、ヘンリー・ファレル(ジョージワシントン大教授)、アブラハム・ニューマン(ジョージタウン大教授)。二人は、三本の「鎖につながれたグローバル化」のリンクを断ち切るのは無理とみる。しかしコロナ禍をめぐるトランプ政権の執拗な対中攻撃をみると、サプライチェーンと情報ネットワークの破断は可能ではないか。
トランプ政権は、冷戦期に共産主義国への軍事技術・戦略物資の輸出規制のために設けた対共産圏輸出統制委員会(COCOM)体制を復活させるかもしれない。5月22日には、中国の33企業・機関を禁輸対象に指定した。COCOMが復活すれば、メディアは「新冷戦復活」と報じるに違いない。
それでも①の「地球規模の金融システム」は断たれていない。新冷戦は回避したいのが中国の本音である。米国はドルによる「グローバル金融システム」を支配し、中国もそのシステムの中で発展してきた。中国の金融機関がシステムから排除されれば、中国経済は破綻に向かう。
◆ 「中国離れ」できない日本企業
これに対し中国側は、保有する1兆8,000億ドルに上る財務省証券を市場に放出する「報復」の選択肢がある。しかしそのカードを切ればドルは紙くずと化し、中国経済のみならず世界経済を破滅に導く。ドルによる国際金融システムに加え、両者の軍事力には3倍から4倍と圧倒的な差がある。中国の強硬な外交姿勢を「戦狼外交」と呼ぶ向きがあるが、国内向けの強気姿勢とみるべきであり、中国に新冷戦を闘う力はない。過大評価してはならない。
安倍政権にとっても他人ごとではない。トランプ政権がデカップリングで中国排除を進めれば、日本政府と経済界も「米国かそれとも中国か」の選択を迫られる。安倍は日米同盟の強化を外交基軸にするが、中国との提携・協力・契約の見直しを迫られれば、日本経済は成り立たない。
安倍政権は4月の緊急経済対策で、サプライチェーンを中国に過度に依存している現状を見直し、生産拠点の移転を支援するため総額2,435億円を第1次補正予算に盛り込んだ。続いて5月には、外国投資家による日本の安全保障に関わる産業への直接投資の監視を強化する「改正外為法」も成立した。
では生産拠点の「中国離れ」は、政府の思惑通りに進むだろうか。伊藤慎吾・国際経済研究所主席研究員[注3]は、中国から生産拠点を分散・移転させる企業は、日米問わず10~20%にとどまっているとし、その理由として ①中国には産業基盤の広さとノウハウの蓄積があり、代替地を見つけるのは簡単ではない ②中国という巨大市場の大きさ―を挙げている。
◆ 「生煮えの陰謀論」
では、米国の一極支配からの退場後に訪れる世界秩序とはどのようなものか。「米中新冷戦」ではないとすれば、米国際政治学者イアン・ブレマーが言う「Gゼロ」(無極化)なのか。英フィナンシャルタイムズのコメンテーターで、米国政治が専門のジャナン・ガネシュ[注4]=写真=は、「Gゼロ」支持者である。

ジャナン・ガネシュ~日本経済新聞HPより
「今の世界がもはや米国の一極集中でないのは明らかだ。だが我々は、最近声高に語られるような二極化した世界に生きているわけでもない」
「米国が西側諸国の感染拡大対策の陣頭指揮を執っているわけではないし、中国が自国に近い国々に感染対策を指示しているわけでもない」。コロナ禍でもリーダー不在とみる。
「冷戦というのは2つの大国が角突き合わせているだけでなく、残りの世界の多くはいずれかの陣営に取り込まれているというのが特徴だ。~中略~(しかし)世界はそれ以上に細分化されている」
米中によるブロック化はあり得ないとの主張である。
結論としてガネシュは「今回の危機の結果として、米中対立が"第2の冷戦"につながるという陰謀論的な生煮えの議論が消え去るのを期待したい」と説く。米国も中国も世界秩序の主導権が取れない時代が続くというのが彼の主張だ。
「Gゼロ」論と、米、中、ロ、EU、インドなどいくつかの「極」が、それぞれ主張し、テーマごとに政策決定する「多極」の世界とは矛盾はしない。
◆ 二項対立に思考誘導
ガネシュが否定する「冷戦」という言葉にこだわる理由がある。「新冷戦論」は、米中対立の内容と性格を規定する単なるワーディング(用語)ではない。経済はもちろん政治、軍事、思想、文化に至るあらゆる領域で「米国か中国か」「民主か独裁か」の二者択一を迫る「落とし穴」に、無意識のうちに誘い込む。複雑な相互依存によって成立している国際政治の世界で、「二択」を迫るアジェンダ設定自体が無理筋というべきであろう。
中国全人代常務委員会は6月30日、香港国家安全維持法を制定した。翌7月1日付の日本経済新聞(朝刊)は、その背景と展望を分析する記事を掲載した。その見出しは「強行した香港国家安全法 民主主義への挑戦状 強権中国と世界」。「一党独裁か民主主義か」の典型的な二分法から、中国の強権政治を批判する内容である。
「一党独裁」の主体が中国共産党であるのは疑いないが、「民主主義」の主体はなんだろう。日本? それとも日本を含む先進工業国?「民主主義」という曖昧な概念の中に、「中国以外の国際社会」をすべて取り込む乱暴な論理が、無意識のうちにタイトル化される。
筆者は、米国のファーウェイ排除を批判する記事[注5]を書いたことがある。これに対しある読者は「アメリカと中国のどちらが良いと聞かれたら、アメリカが良いと言うしかないね。残念だけど」とツイートした。これが「二項対立」によって誘導された意識である。
「新冷戦派」の論法は、米中のあらゆる争点を「体制間対立」というアジェンダに引き込む。香港問題をはじめ台湾問題もコロナ禍も同様だ。そしてこの戦術は一定の成果を収めている。
「独裁か民主か」の二択を迫られれば、代表制民主に慣れた人々は果たして「独裁」を選択するだろうか。筆者も「独裁」を選択しない。しかし、独裁と同質のガバナンスをもたらすポピュリズムを生み出したのは、紛れもなく「民主主義」であり、民主の内実もまた問われていることを自覚しなければならない。
◆ 中国は新リーダーにはなれない
「サプライチェーン」の再構築は、世界経済再生にとって必須の条件であり、経済合理性がある。だが人も国も必ずしも合理性に基づいて判断し行動しているわけではない。中国はコロナ後、自由貿易と多国間協力の旗手になるだろう。繰り返すが、米退場後の世界で、その空白を埋めるリーダーになるとみるのは、過大評価である。
中国は3月に感染爆発を起こしたイタリアやスペインなど欧州諸国への医療支援を中心に「マスク外交」[注6]を展開してきた。だが欧州の反応は歓迎一色ではない。中国の影響力が強まる中、中国を「戦略的競争相手」「体制上のライバル」(「EU・中国戦略概観」=2019年3月)とみなす警戒の声も高まる。
中国自身もそのことをよく理解している。中国外務次官を務めた傅瑩氏(清華大戦略安保研センター主任)は4月27日付けの中国紙「参考消息」[注7]とのインタビューで、「(米中)両国が不毛な競争を続け、さらに『デカップリング』と対決に向かい、どちらの側につくか他の国に迫るならば、世界を分裂に向かわせることになる。それは双方の利益を損なうだけでなく、世界の安定をも壊すことになる」と警告し「世界の他の国は中米のどちらかの側につくことを望んではいない」と述べた。
イアン・ブレ―マーが説くように、コロナ後の世界は当面「主導国なき時代」が続くだろう。サプライチェーンを再構築する上でも、新冷戦という「思考の落とし穴」にはまるのは避けねばならない。
◆ それでもトランプがまし
「米中新冷戦」をまじめに論じるのが、ばかばかしくなる本が米国で出版された。ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障担当)が6月23日に出版したトランプ暴露本『それが起きた部屋』(The Room Where It Happened)=写真=。彼はトランプが習近平らと交わした会話内容を暴露しながら、対中政策のすべてが再選優先のためだと批判する。
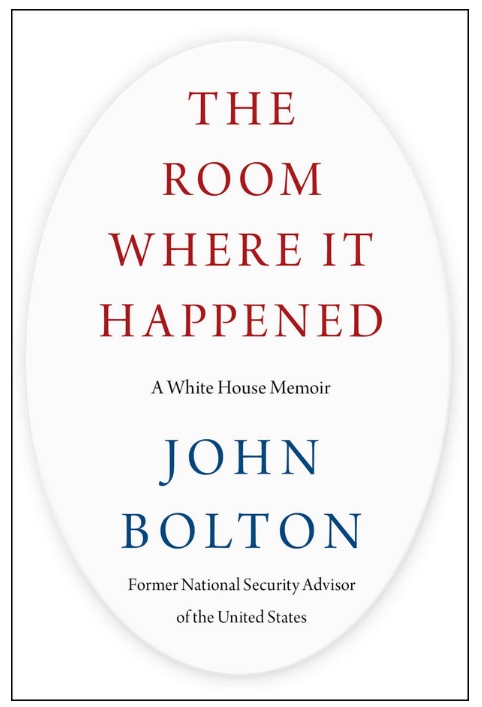
『それが起きた部屋』表紙
例えば、2019年6月末大阪で行われた米中首脳会談。トランプは習を「中国史で最も偉大な指導者だ」と、歯が浮くような言葉で持ち上げながら、中国が農産品購入を増やせば大統領再選に「追い風になる」と述べたという。一方、習が米国の中国批判グループに不満を述べると、トランプは「民主党は中国に大きな敵意を持っている」と答えた。民主党の大統領に代われば「反中国」はさらに強まるから「オレを支持しろ」という意味だ。
さらに、習が新疆ウイグル自治区で建設している収容施設の正当性を主張したのに対し、トランプは「施設の建設を進めた方がいい」と述べたとされる。また貿易協議を優先し、香港のデモを擁護しない姿勢も示した。
その習会談の1年後の2020年6月17日、トランプはウイグル族弾圧に関与した中国の当局者への制裁に道を開くウイグル人権法に署名し、同法は成立した。ボルトンの指摘通り、トランプの「取引外交」の動機が、大統領再選にあるのは間違いない。トランプ自身は決して対中国強硬派ではない。イデオロギーとは無縁のビジネスマンと考えたほうがいい。
米国政治は「一枚岩」ではない。ホワイトハウスに国務省、国防総省、議会などの主体は、お互いにけん制し合いながら、時には「敵対」し合う関係にある。しかし大統領の発言と、政権の対中政策がこれほど乖離した例はあまりない。
中国もそのあたりを冷静に読んでいる。中国の米国研究の重鎮、王緝思・北京大教授[注8]のトランプ評価をみてみよう。ボルトンの暴露とピッタリ重なるのが興味深い。11月の大統領選で習近平政権が、トランプ再選に期待していることがよく分かるはずだ。
「トランプは主に経済と貿易の問題で中国と張り合っており、南シナ海問題、台湾問題、香港問題、人権問題、新彊問題等については大きな関心を寄せていない。更に言えば極端な反中勢力を抑え込み、経済と貿易の問題を処理した後にその他の問題を解決すると表明している。バイデンが当選したら、中国の内政問題、南シナ海の問題、国際問題において、トランプより更に度を越した対応をする可能性がある」
ボルトンは米中関係の最大のトゲである台湾問題でも、トランプが再選を果たしたら台湾を「見捨てる」ことは十分あり得ると書いている。
[注1] 朝日新聞社説「コロナと米中 覇権争いの時ではない」4月17日付
https://www.asahi.com/articles/DA3S14444809.html
[注2]「Chained to Globalization Why It's Too Late to Decouple」(FOREIGN AFFAIRS January/February・2020)
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2019-12-10/chained-globalization
[注3] 『コロナ後』のグローバル・サプライチェーンと中国」(「外交」Vol・61 May/Jun・2020)
[注4] ジャナン・ガネシュ「コロナ危機で露呈、無極化した世界」(日本経済新聞デジタル版 4月10日)
[注5] 「日本は米国忖度だけでいいのかファーウェイ排除の根拠は?」
https://www.businessinsider.jp/post-181625
[注6]「マスク外交」で中国は世界のリーダーになれるか。「健康シルクロード」提唱
https://www.businessinsider.jp/post-211326
[注7] 战疫:观察与镜鉴| 清华大学战略与安全研究中心主任傅莹:美强硬势力毒化中美合作气氛
http://ihl.cankaoxiaoxi.com/2020/0427/2408726.shtml
[注8] 王緝思「新型コロナウイルス流行下の米中関係」(笹川日中友好基金 4月30日)
https://www.spf.org/china/news/20200430.html
(***)