【書評】
瞋る怨霊の結集
『非=戦(非族)』添田 馨/著 響文社/刊
現実をなぞるのではなく、それ自身の表出として成り立って初めて詩は成立する。それゆえ詩は現実と一線を画す批評を内在させずにはおかない。戦後詩が批評性を際立たせたのは、戦中期に詩がこぞって大政翼賛的に時代に迎合し自滅したことへの猛省にあった。そのため戦後詩は、左右のいずれに対しても、批評性を手放すまいとする限り孤立を余儀なくされてきた。このため戦後詩は大衆的に迎えられることは一度とてなかったが、論壇や文壇が妥協することで成ったのに対し、戦争責任論、戦後責任論において知る人ぞ知る突出した展開をもった。
しかし、この誉れが七〇年代の大衆消費社会の到来に始まる資本主義社会の変質と大衆の過剰な欲望の中で機能しなくなったのは、戦後詩がそれに総体的対応しうる構造的な批評体系を確立しえなかったことによる。そのため複雑に高度化した社会に対応せんとして、戦後詩はいきおい修辞に頼らざるをえなくなった。この後退戦においての修辞の重畳はその泥沼化に拍車をかけた。それは九〇年代の終焉後にあっても克服されることはなかった。
そうした中、2004年に添田馨は詩集『語族』を上梓し、突然変異する。その変異は某地を訪れた偶然に始まる。そこに時層の異なる遺物の重層する展開の表層に浮かぶ現在を見た添田馨は、皮相としての現在を確認したに等しい。それは単層的表出から複眼的表出へと添田馨を突如、変身させることになった。それは今を跋扈する生霊の大地深く、無念の涙を呑んだ無数の死霊の声を聞いたに等しい。それはあったがままの歴史事実の回復以外を望んでいないのである。これ以後、添田馨の詩語は、層を成すとりどりの死霊との交感によって生じた語族として、邪な現実を包囲し、照射する自覚に燃えることになった。その語族としての自覚をこう記す。
私とは、消え去ったとある語族の亡霊だ。/どんな構築をも放逐し/イメージの発掘だけでおのれの出自を問う者だ。
語族の一員に列した添田馨のする修辞は、修辞の至らなさを修辞で補うに似たこれまでの後退戦とちがい、歴史に裏付けをもった死霊による生霊への反転攻勢で、それ自体が批評的表出としてあるため、その表出は、ことごとく現代詩の前線を張ることになった。それは現在という嘘を紡ぎ出した生霊の(神ノ手)の秘密をこう捉える。
世界を言い換える舌が/そのあとに植えられる/黄金の稲穂のそよぎを国語となして/邪馬臺を「大和」に/東日流を「津軽」に/日高見を「北上」に/美しく言い換える舌ばかりが/言葉を紡ぎ足していった/神の手はつねに一本/地面を掘り返す指は/あらゆる魔法で歴史を作った/かくして江戸は東京になり/つねに無傷でわが皇国は脱皮をつづけた
こうした添田馨の営為はその達成に見合った詩を踏まえ、詩論、平和論、経済論、古代史論等々において多面的展開をもつことになった。詩集としては、3.11の東日本大震災による被災地が故郷に重なったこともあり、一九八五年以降の故郷への想いを込めた習作を集成した『樹羅森象』(2012年)は、東北への鎮魂詩集としてある。それに陸続し、上古まで遡るフォークロアへの関心は詩集『民族』(2013年)として結実する。
前者にあって添田馨は、突如、プラタナスの樹に話しかけられた異常体験を語るが、それは宇宙から逆さに屹立した宇宙樹へ幻視を進めている。この特異体験が『語族』での突然変異に連続しているかに見える。後者の『民族』は歴史が身体をもっていることに気づいたところからするこの列島の伝統や信仰が、如何に生霊によってねじ曲げられて日本国の現実として成ったかとする呪詛詩ともいえるもので、その考察の深度は深い。
起源の物語が消え去って久しい/流離の山河を茫々と吹き抜ける颱風は/死滅した国家の亡民の生い立ちから/その戦意の広大な裾野に草々の兵隊を/渡来した種苗に運んだ/もう何世代も前から私の胸には/金色に光輝く日の巫女の面影が宿り/プヨー族の女は武器と太鼓を選ばない/プヨー族の男は戦いの踊りを冠飾りに変えて/草原を南下する道を選んだ/正統な王権のもと神話は幾星霜の戦闘を浄化した
このプヨー族が扶余族を指し、日の巫女が卑弥呼を指し、北方騎馬民族の南下策に従って列島に侵攻し・列島王権を簒奪したとする、通説を遙かに凌駕した歴史的認識を、どれほど理解する人がいるだろう。
今回、発刊を見た『非=戦(非族)』は、民主党政権の自壊が再登場を許した安倍政権の強権政治への、それを許すまじとする今を生きる怨霊と連帯した添田馨の存在をかけた瞋りのプロテスト詩の試みである。安倍内閣が平和主義・国民主権・基本的人権の尊重を三柱とする日本国憲法を戦後レジームと悪罵し、その滅却を憲法改悪を着地点に見据え、日米安保体制の海外展開を憲法枠を越えて自衛隊の紛争地域への積極的展開をはかり、秘密保護法からテロ等準備罪を法案化し、それらを閣議決定による強権政治の展開は、国政の最高機関としての立法府の無視に止まらず、国民主権の侵害以外の何ものでもない。
これらを、いたずらに東アジアの危機を煽り、中朝の軍拡路線への対抗させる安全保障を歌い文句に、安倍一強の自民党体制を公明党を取り込んで成立させてきた。そのごり押し政治は来年の憲法改悪の正念場を前に、お友達への利益供与疑惑でほころびを見せているとはいえ、戦後世界の大戦の反省を脅かす国際資本や極右勢力と連携し、世界潮流を生み出してきた。安倍晋三が率先してトランプ大統領に媚びを売ったのは当然である。そうした中での本詩集の発刊は、その安倍強権政治の第二展開当初から抗議意思を鮮明にし、添田馨は安倍政権への国会周辺での抗議デモや集会に率先して関わりつつ、本詩集を集成したので、それは行政府を占拠した安倍政権への義憤の表明である。それは単なる指示表出からする反対語の羅列ではなく、とりどり歴史的存在の義憤を汲み上げた語族としての表明なのだ。
義憤はどこからやって来たか/国柄への悲嘆から義憤はやってきた/利権が食い荒らした/幾山河からやって来た/借財が踏み潰した/名もない村々からやって来た/安眠の森を奪われた/遠すぎる島々からやって来た/宿主のない無言の怒りは/国土の隅々からやって来た/蹶起をきめた我々の意志は/もはや爆発寸前だった/激情は鬱勃と滾り立っていた
それは現在どれほどの危機にあるかの添田馨の危機意識を語り、その抗議は上古からの日本的な詐術支配の洞察をともなった展開となっている。それは戦中の戦争参加を奏でた辻詩集や、戦後の反戦詩集に引き継がれた安易な便乗詩の限界を、この列島の歴史的実存を踏まえての詩的展開となっている。
そのタイトルに見られる造語・『非=戦』(非族)について、本詩集付録の生野徹との対談で添田馨は、非族の表記は二種類あって、漢字二文字の「非族」とダブルハイフン付きの「非=族」の、まったくちがう概念を包含したとする。換言すれば前者は non-folks =民族ならざる者、後者は non-natives =土着ならざる者を指すとし、《ふたつは全く別々の対象とも言い切れなくて、対象化された存在が「非族」で、内在化された存在が「非=族」とする同一者を両義的に捉える言い方》とし、「=」は単なる記号ではなく一つの文字としてあると言う。それは「プロセスとしての戦争」を「戦=闘」と表記したのに対し、「非=戦」が戦争への全体的なアンチテーゼとして、「反戦」や「不戦」とちがい、「戦=闘」に全体的に抗っていく行動や思想の全てを網羅したものとする。これはプラタナス体験や語族としての覚醒にあった、歴史が身体性をもつことへの自覚から生まれた、恥知らずのヤヌスのごとき表裏を使い分ける現実に、対峙させる詩語の両義性を踏まえての発言に見える。
〈非族〉頌に始まり非=戦で締めくくられる本詩集は、戦後の非戦の誓いを忘れ、逆コースを辿る政府ゆえに、アラブで犠牲になった二人から、戦後、政府に死をもって抗議した多くの人たちへの鎮魂と哀悼を示しつつ、添田馨の安倍政権への瞋恚は最後の千行詩である非=戦まで鎮まることなく、こうリフレインし続ける。
日比谷公園は深い闇のなかにある/総理官邸も同じ闇のなかにある/闇からの沈黙の声が/総理、あなたには聞こえるか/原罪を背負おうとせぬ者よ/広き門しか見ない者よ/世界の裏口から侵入し/収奪だけを生業にする者よ/邪悪の血統はどこまでも邪悪だ/狭量な額には獣の烙印を/邪悪な舌には焼けた鉄こそが相応しい
(古代研究・奪回 代表)
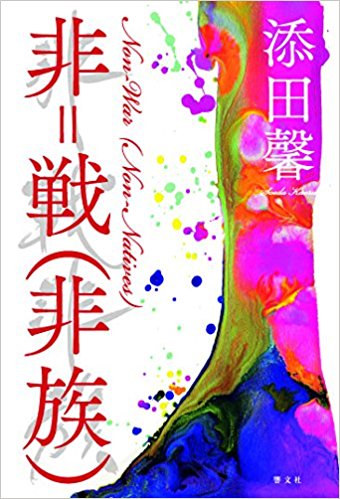
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新号トップ/掲載号トップ /直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧